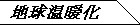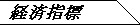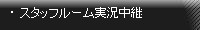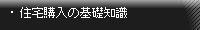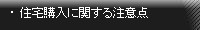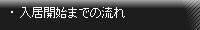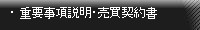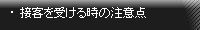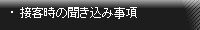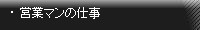重要事項説明書
重要事項説明書に記載されている「瑕疵担保責任の履行に関する保険」の中の、保証金の供託について、見ていこう。
法務局管轄の供託所に、事前に保証金を供託することで、売主に支払い能力がなくなった際に、被害者がその保証金の還付を受けるもの。
保証金の還付を受けるのは、瑕疵担保責任の義務を負う業者が倒産した場合などの緊急事態のみ。したがって、保証金を供託している場合の、瑕疵担保責任に基づく損害賠償は、保証金の還付ではなく、業者が支払う。
供託を行う時期は、法律施行後の基準日。基準日は、原則、法律施行後の3月31日と9月30日の年2回。この日に、業者の過去10年間の供給戸数を確認して、その供給戸数を基に金額を算出し、供託する。当然、供給戸数が多ければ、供託する額も大きい。
要するに、いくら供託するかは、業者の過去の10年間の供給実績によって決まる。
また、住宅瑕疵担保履行法の施行後、一番最初に供託を行うのは、平成22年3月31日となる。
では、最初の基準日である平成22年3月31日に、過去10年間の供給実績をもとにして、保証金を供託するのか?
この場合は、施行の時点から、最初の基準日までの供給戸数をもとに金額を算出する。法律施行後10年間は、経過措置となるため、施行の時点で、いきなり過去10年間、というわけではない。
そして、半年ごとに、保証金の算出対象となる供給戸数をプラスしていく。つまり、法律施行後10年間が経過するまで、過去10年間の実績にさかのぼっては計算されない。
保証金の供託
法務局管轄の供託所に、事前に保証金を供託することで、売主に支払い能力がなくなった際に、被害者がその保証金の還付を受けるもの。
保証金の還付を受けるのは、瑕疵担保責任の義務を負う業者が倒産した場合などの緊急事態のみ。したがって、保証金を供託している場合の、瑕疵担保責任に基づく損害賠償は、保証金の還付ではなく、業者が支払う。
供託を行う時期は、法律施行後の基準日。基準日は、原則、法律施行後の3月31日と9月30日の年2回。この日に、業者の過去10年間の供給戸数を確認して、その供給戸数を基に金額を算出し、供託する。当然、供給戸数が多ければ、供託する額も大きい。
要するに、いくら供託するかは、業者の過去の10年間の供給実績によって決まる。
また、住宅瑕疵担保履行法の施行後、一番最初に供託を行うのは、平成22年3月31日となる。
では、最初の基準日である平成22年3月31日に、過去10年間の供給実績をもとにして、保証金を供託するのか?
この場合は、施行の時点から、最初の基準日までの供給戸数をもとに金額を算出する。法律施行後10年間は、経過措置となるため、施行の時点で、いきなり過去10年間、というわけではない。
そして、半年ごとに、保証金の算出対象となる供給戸数をプラスしていく。つまり、法律施行後10年間が経過するまで、過去10年間の実績にさかのぼっては計算されない。
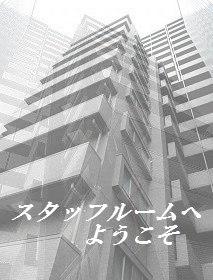 |
| <瑕疵担保責任の履行に関する保険> |
|---|
| ・瑕疵担保責任の履行に関する保険の説明義務 |
| ・住宅瑕疵担保履行法とは? |
| ・住宅瑕疵担保履行法の対象 |
| ・住宅瑕疵担保責任保険法人の指定 |
| ・紛争処理体制の整備 |
| ・保証金の供託 |
| ・保険の加入 |
| ・住宅瑕疵担保履行法に関する疑問点 |
| ・重要事項説明13 - 瑕疵担保責任の履行に関する保険 |
| ・重要事項説明・売買契約書 - TOP |